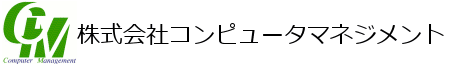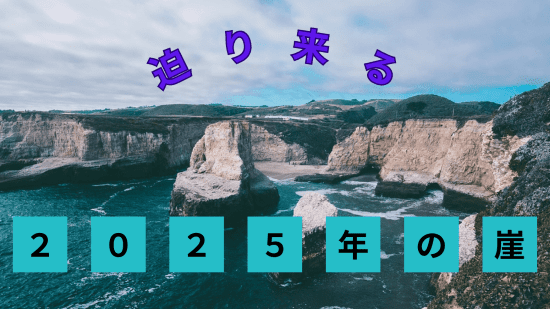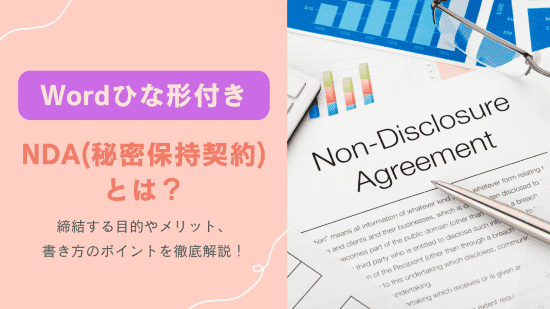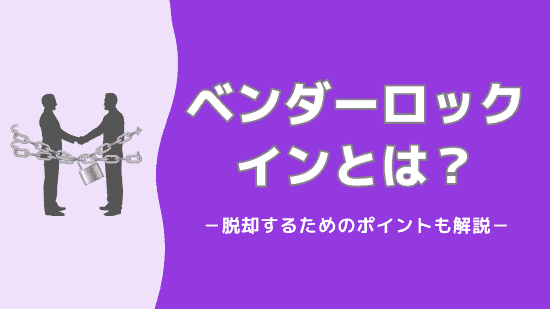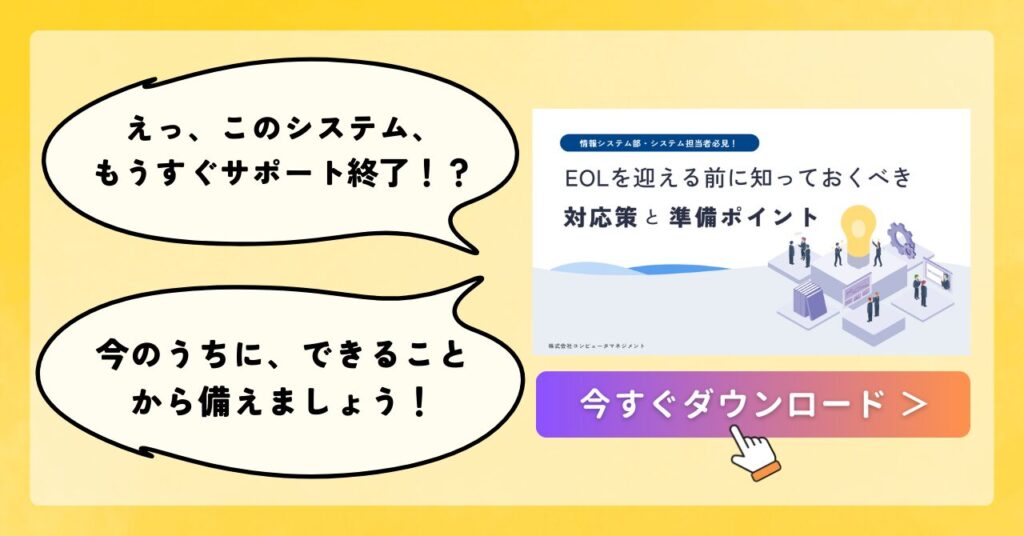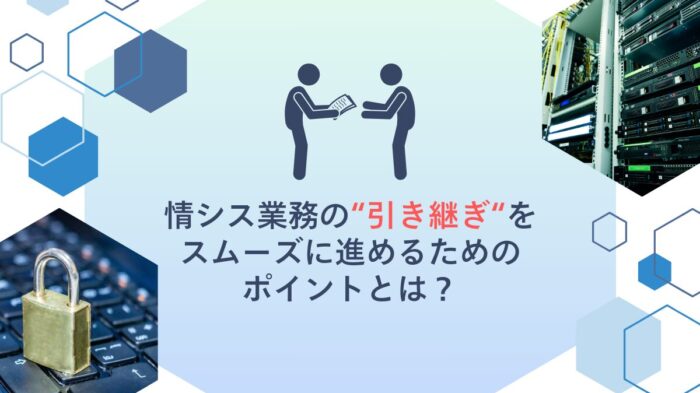
人事異動や退職に伴う業務の引き継ぎは、企業にとって避けては通れない課題の1つです。
特に、社内のITに関する業務を一挙に担う情報システム部門で引き継ぎが上手くいかないと、業務の停滞やセキュリティリスクの増加など、会社全体に深刻な影響を及ぼしかねません。
こうしたリスクを最小限に抑え、スムーズな引き継ぎを実現するためには、どのような点に気を付けるべきなのでしょうか?
今回は、情シス業務の引き継ぎを進めるうえでの基本的な手順や、引き継ぎ資料を作成する際のポイント、引き継ぎ時の注意点などについて詳しく解説します。
目次
1.情シス業務引き継ぎの重要性と放置リスク
情報システム部門では、担当者の異動や退職、システム保守ベンダーの変更時などに、必ず引き継ぎ作業が必要になります。
引き継ぎが十分に行われないと、業務の停滞やセキュリティリスクの増加といった問題が発生し、社内だけでなく顧客や取引先にも深刻な影響を及ぼす可能性があるため、慎重かつ計画的な対応が求められます。
情シス業務の引き継ぎが不十分なために生じるリスクとしては、主に次のようなものがあります。
- 属人化による業務の停滞
- セキュリティリスクの増加
- サービス品質・信頼の低下
- ナレッジ・ノウハウの喪失
属人化による業務の停滞
特定の担当者だけが業務の進め方やノウハウを熟知している「属人化」の状態が続くと、その担当者が異動・退職・休職などで突然不在になった場合に、システム運用やトラブル対応が滞り、業務が停止するリスクがあります。
特に、過去にあったトラブルやその対応方法が共有されていないと、同じような問題が再発しやすくなり、対応の遅れによって業務全体に影響が広がります。
セキュリティリスクの増加
引き継ぎが不十分だと、セキュリティに関する設定や運用状況が後任者に正しく伝わらず、脆弱性が放置されるリスクが高まります。
特に、パスワードの更新やアクセス権限の管理が適切に行われないと、情報漏えいなどの重大なセキュリティ事故につながることがあります。
サービス品質・信頼の低下
引き継ぎが不十分なままだと、後任者が業務内容を正確に把握できず、手探りでの対応を強いられるため、業務の質や効率が大きく低下し、ミスや遅延が発生しやすくなります。
結果として社内ヘルプデスク対応にも支障をきたし、ユーザー満足度の低下を招くほか、業務上のミスや遅延が社外にまで影響を及ぼすと、顧客・取引先からの信頼を損なう可能性があります。
ナレッジ・ノウハウの喪失
引き継ぎが適切に行われないと、前任者が持っていた業務上のコツや知見が後任者に受け継がれず、後任者は非効率なやり方で業務を進めることになります。
知識やノウハウが社内に蓄積されないため、組織全体としての成長・改善のスピードが落ち、中長期的に見て大きな損失となってしまいます。
2.引き継ぎの基本ステップ
情シス業務の引き継ぎは、基本的に次の4つのステップに沿って進めていきます。
- 業務内容の棚卸し
- 引き継ぎスケジュールの決定
- 引き継ぎ資料の作成
- 後任者への引き継ぎ
業務内容や会社の規模によって引き継ぎ期間は変動するため、余裕を持って早めに準備を進めることが大切です。
①業務内容の棚卸し
まずは、現在担当している業務をすべて洗い出したうえで、引き継ぎが必要な業務を選定します。
「システム保守」「インフラ管理」「セキュリティ対策」「ヘルプデスク」など、業務をいくつかの大きなカテゴリーに分け、分類ごとに細かな作業をリストアップしていくことで、抜け漏れを防ぐことができます。
なお、業務の棚卸しを行ううちに、不要な作業や形骸化している作業、改善の必要な作業が見えてくることがあります。
こうした場合は関係者と相談し、引き継ぎ項目から除外するか、実情に合わせてアップデートすることで、無駄な作業を削減できるとともに、引き継ぎもスムーズに進められます。
②引き継ぎスケジュールの策定
業務の棚卸しが完了したら、次は引き継ぎの計画を立てていきます。
引き継ぐ業務の量や難易度などを考慮したうえで、引き継ぎ完了日から逆算してスケジュールを組み立てましょう。
前任者も後任者も、通常業務と並行して引き継ぎ作業を進めなければならないケースがほとんどのため、余裕を持ったスケジュールを立てることが大切です。
前任者が最後に出社する日の1週間前か、最低でも3日前には引き継ぎを完了できるように、無理のない実現可能なスケジュールを作成しましょう。
③引き継ぎ資料の作成
策定したスケジュールに従い、引き継ぎ資料を作成していきます。
自分にとっては当たり前のことであっても、初めてその業務を担当する人にとっては理解が難しかったり、判断に迷ったりすることも考えられます。
後任者が引き継ぎ資料を見て迷わず業務を進められるように、必要な情報は漏れなく記載するように心がけましょう。
詳しくは後述しますが、引き継ぎ資料を作成する際のポイントとして、次のようなことを意識してみましょう。
- 分かりやすい言葉を使う
専門用語や難しい言葉は避け、誰でも理解できる言葉で説明する - 見やすさを意識する
短く簡潔な箇条書きにし、重要なポイントを視覚的に強調する - 図表を活用する
文章だけでなく、図やスクリーンショットを使って直感的に理解しやすくする - 章立てを明確にする
目次(大項目・中項目・小項目)を先に決め、順を追って記載する - 必要な情報を網羅する
後任者がスムーズに業務を進められるよう、必要な情報を漏れなく記載する - 経験から得たノウハウを記載する
業務から得た知識・経験など、システムやツールのマニュアルには載っていない情報を含める - セキュリティへの配慮
IDやパスワードなど、機密情報の取り扱いに注意する - 業務スケジュールの整理
年間スケジュールや月間スケジュールに分けて作成する
④後任者への引き継ぎ
引き継ぎ資料が完成したら、策定したスケジュールに従って後任者への引き継ぎを実施します。
ただ単に引き継ぎ資料を共有するだけでなく、対面やオンラインで資料の読み合わせと質疑応答の時間を設け、認識の食い違いや疑問点をその場で解消することが好ましいです。
余裕があれば、前任者のフォローのもと、実際に後任者に業務を任せてみて、実践の中で理解を深めてもらうことで、後任者は自信を持って今後も業務に取り組めるようになります。
なお、資料の読み合わせや実践の場において、後任者から疑問点が出てきたり、ドキュメントの不備や情報の不足に気付いた場合は、忘れないうちに速やかに追記・修正を行い、資料のブラッシュアップを図りましょう。
3.引き継ぎ資料に記載すべき内容
引き継ぎ資料に記載すべき項目としては、次の10個が挙げられます。
- 業務概要・目的
- 月間・年間スケジュール
- 業務フロー・手順
- 社内システム概要
- ドキュメント一覧
- 資料や必要書類の保管先
- 社内外の関係者一覧
- 過去にあったトラブル・対処法
- 業務のコツ・ノウハウ
- 現状の課題(未処理事項・懸念事項)
業務概要・目的
「どんな業務か」「なぜその業務を行う必要があるのか」「業務の目的は何か」などを記載します。
業務の目的や全体像を理解していないまま仕事を進めてしまうと、目の前の作業をただこなすだけになってしまい、想定外の事態に対応できなかったり、トラブル対応を誤ったりするリスクが高まります。
背景や意図を理解していることで、後任者は納得感を持って業務に取り組むことができるほか、状況に応じた柔軟な対応や判断ができるようになります。
具体的には、次のような内容を記載すると良いでしょう。
- 業務についての大まかな説明
- 業務の背景・経緯
- 業務の遂行によって達成したい目的
- 社内での業務の位置付け
なお、業務内容は「定期/臨時」「作業ボリュームの大小」「緊急度」などの軸で分類しておくと、後任者の理解もスムーズです。
年間・月間スケジュール
年間スケジュールと月間スケジュールの両方を記載します。
スケジュールを可視化することで、後任者が業務全体を把握しやすくなるほか、業務の抜け漏れを防ぐ効果も期待できます。
【年間スケジュール】
・・・年度始めから終わりまでの1年間の業務スケジュール
- 担当する業務をすべてリストアップし、月ごとに分ける
- 業務の対象期間は、線や矢印を使って視覚的に示す
- 業務ごとに簡単な作業概要も加えておく
(細かい業務内容まで書く必要はない)
【月間スケジュール】
・・・毎月の業務スケジュール
- 作業ごとの期限を時系列順に記載する
- 期限は「第〇営業日」「月末」など具体的に
- 報告先(自部門、他部門、取引先など)も明記する
- 必要な作業時間の目安も伝えておく
業務フロー・手順
日々の業務手順を分かりやすく記載します。
特に、定型的な業務は手順化されていることが多いため、画面キャプチャや図解を積極的に取り入れながら、業務の流れに沿って具体的な作業ステップを明記しましょう。
単に「何をするか」だけではなく、「なぜその手順なのか」「作業の目的は何か」といった業務の背景や理由、他業務とのつながりも含めて説明すると、後任者の理解が深まります。
作業手順は箇条書きでも構いませんが、専門用語や社内特有の言い回しは避け、誰が読んでも分かりやすい表現を心がけましょう。
社内システム・インフラ概要
情シス業務の中核をなす部分であり、後任者が全体像を把握するうえで欠かせない重要な情報として、社内システムやインフラの概要を記載します。
具体的には、次のような情報を盛り込んでおくと良いでしょう。
社内システムの概要
- 各システムの名称・用途:何のためのシステムか
(例:勤怠管理、顧客管理など) - 導入目的・背景:なぜこのシステムが導入されたのか
- 利用部門・ユーザー:誰がどのように使っているか
- 業務との関係性:どの業務プロセスに関わっているか
- システムの構成:クラウド/オンプレミスなど
- 運用ルール・頻度:どのタイミングで何を行う必要があるか
- 保守契約の有無:ベンダー情報、契約内容、問い合わせ先など
- 今後の課題・改善点:現在抱えている問題や改修予定など
社内インフラの概要
- ネットワーク構成:社内LAN、VPNなど
- サーバー構成:物理/仮想、オンプレ/クラウド、用途、設置場所など
- 利用中のクラウドサービス:Microsoft 365、Google Workspace、AWS、Azureなど
- ストレージ・バックアップ体制:データの保存場所、バックアップの方法や頻度
- セキュリティ対策:ウイルス対策ソフト、ファイアウォールの設定、認証方法など
- ライセンスの管理状況:契約更新日やライセンスの有効期限など
関連ドキュメント一覧
業務や社内システム、インフラ関連のドキュメントを一覧にして整理します。
記載しておくと良いドキュメント例は次の通りです。
業務関連資料
- 業務フロー図:業務プロセスを可視化した図
- 業務マニュアル:各業務の手順やルールを記載したマニュアル
- 担当業務一覧:現在の業務内容や担当者の一覧
- 各種テンプレート:報告書や会議資料のテンプレート
- 問い合わせ対応マニュアル:ヘルプデスクの対応マニュアル
システム関連資料
- システム構成図:利用しているシステムの全体構成図
- システム仕様書:システムごとの機能仕様、画面仕様、帳票仕様など
- データフロー図(DFD):データの流れを可視化した図
- ER図(エンティティ関係図):DBの構造を示す図
- テーブル定義書:DBにおける各テーブルの項目名、型、制約条件などの詳細
- システム運用マニュアル:日次・月次業務、障害対応などの手順書
インフラ関連資料
- ネットワーク構成図:社内LANやVPN、ファイアウォールなどの構成
- サーバー一覧:利用中の物理/仮想、クラウド/オンプレサーバーの情報(役割・スペック)
- サーバー設定仕様書:OS設定、サービス設定、ミドルウェア構成など
- バックアップ手順書:バックアップ対象、頻度、保存期間、復旧手順
- ライセンス・契約管理台帳:利用中のソフトウェア・OSのライセンス数、契約更新日など
- アカウント管理ポリシー:権限設計、ID発行・削除ルール、パスワードポリシーなど
- 障害対応マニュアル:障害発生時の初動対応・連絡フロー
- セキュリティポリシー:インフラ全体に対するセキュリティ方針
資料や必要書類の保管先
後任者が必要な資料にすぐアクセスできるよう、引き継ぎ資料にはドキュメント類の保管場所も必ず明記しておきます。
単に保管場所を記載するだけでなく、可能なら共有フォルダに直接アクセスできるURLリンクも記載しておくと親切です。ただし、リンク切れには十分注意しましょう。
「ドキュメントの名前は分かるけれど、どこにあるか分からない・・・」という事態を防ぐためにも、忘れずに記載しておきましょう。
社内外の関係者一覧
業務内容に関して分からないことがあった場合や、システムトラブルが発生した場合などに、すぐに適切な相手に連絡を取って対処できるよう、各関係者の連絡先を明記します。
- 社内関係者:システム管理者、主要ユーザー、各業務の担当者など
- 社外関係者:システムベンダー、保守業者、外部パートナーなど
各関係者の名前、役職、担当分野、連絡先(電話番号・メールアドレスなど)を明記し、「どのような場面で」「誰に」連絡すればよいか一目で分かるように整理しておくと、いざという時の対応がスムーズに進みます。
イレギュラー対応の詳細
過去のトラブル例をもとに、想定外の事態が発生したときの対応手順や、連絡・エスカレーションのルールを明確に記載しておきます。
- 実際にあった過去のトラブル事例
- システム障害が発生した場合の初動対応
- 特定のエラーが発生した際の対応フロー
- サポートしてくれる部署名や連絡先
などをあらかじめ整理しておくことで、後任者がイレギュラーな事態に遭遇しても慌てずに対応できる環境を整えられます。
業務のコツ・ノウハウ
慣れている人しか知らないコツや、実際の経験に基づくノウハウなど、後任者が効率良く業務を進めるうえで役に立ちそうな情報があれば記載します。
- 作業をスムーズに進めるためのちょっとした工夫
- 過去のトラブルから得た教訓
- トラブルを未然に防ぐための注意点
- 関係部署とのやり取りで気を付けるポイント
- 社内ルールに明文化されていない「決まりごと」
など、自分が経験して「これは知っておいて良かった」と感じた”現場の知恵”は、ぜひ記録として残しておきましょう。
現状の課題(未処理事項・懸念事項)
現時点で未解決のまま残っている課題・トラブルや、今後起こり得る懸念事項があれば、一覧にして記載しておきます。
記載漏れと誤解されないよう、特に問題がない場合は「なし」と明記しておきましょう。
ここでは、各課題や懸念事項の優先度・重要度を明記しておくことで、後任者がどれから優先的に対応すべきか判断しやすくなります。
さらに、「課題が発生した経緯」や「これまでに検討した内容」も記載しておくと、事情を知っている分トラブルの早期解決を目指せるほか、後任者が同じ検討を1から繰り返す無駄を防げます。
4.引き継ぎ資料を作成する際のポイント
引き継ぎ資料の作成時に押さえておくべき7つのポイントをご紹介します。
- 初めて業務を担当する人でも理解できる構成にする
- 文章だけでなく図や表も活用し、視覚的に伝える
- 手順だけでなく業務の目的や背景、トラブル対応方法も含める
- 困った時に相談できるよう、すべての関係者を洗い出す
- 口頭での説明に頼らず、どんな細かいことでも漏れなく記載する
- 慣れている人しか知らないノウハウやTipsも残しておく
- 資料通りに問題なく業務が進められるか検証する
初めて業務を担当する人でも理解できる構成にする
引き継ぎ資料は、初めて業務を担当する人でも理解できるように作成することが重要です。
自分にとっては当たり前のことでも、後任者が知っているとは限らないため、難しい専門用語や独特の社内用語は避け、誰にでも分かるシンプルで丁寧な表現を心がけましょう。
また、見出しや箇条書きを積極的に活用して、資料全体を隅々まで読まなくても、大まかな流れやポイントが一目で分かる構成にするとさらに効果的です。
全体像を把握しやすく、必要な情報にすぐアクセスできるようになるため、実用性も高まります。
文章だけでなく図や表も活用し、視覚的に伝える
資料を作る際に、文章のみに頼っていては内容が抽象的になり、読み手の誤解や理解不足を招く恐れがあります。
図やフローチャート、スクリーンショット、動画などの視覚的な要素も取り入れて、情報が正しく伝わるように工夫することが大切です。
- 全体像を把握しやすいようにシステム概要図や相関図を作成する
- 操作手順をスクリーンショット付きで解説する
- 時間経過による状況変化が分かりやすいようにフロー図を活用する
- 決まった時期に繰り返し行う定型業務をスケジュール表形式でまとめる
など、図表や画像キャプチャを使って整理しながら、誰が見ても具体的に業務をイメージできるような資料を目指しましょう。
手順だけでなく業務の目的や背景、トラブル対応方法も含める
引き継ぎ資料において、業務の進め方や手順を伝えるだけでは不十分です。
その業務を行う目的や背景、注意点、全体の流れ、他の業務との関係性も含めて丁寧に説明しましょう。
「なぜその業務が必要なのか」「その業務が組織の中でどのような役割を果たしているのか」「何の業務とどのように関係しているのか」を明確に示すことで、後任者は業務の位置付けを正しく理解し、状況に応じた適切な判断ができるようになります。
さらに、過去に発生したトラブルやよく問題が起こりやすい箇所、その際の対処法など、イレギュラー対応に関する情報も記載しておくと、業務に不慣れな後任者の不安を和らげることができます。
困った時に相談できるよう、すべての関係者を洗い出す
引き継ぎ資料には、社内・社外含め業務に関わるすべての関係者を漏れなく記載しましょう。
社内の担当者だけではなく、外部のベンダーやパートナーなど、関係者全員の名前や連絡先を明示しておきます。
これにより、トラブルや困りごとがあった際も誰に相談すべきかすぐに分かり、迷わず適切な相手に連絡を取って、業務を円滑に進めることができます。
口頭での説明に頼らず、どんな細かいことでも漏れなく記載する
引き継ぎ資料は「必要な情報がすべて揃っている」ことが重要なポイントです。
特に、年に数回しか発生しない業務や、合間で無意識に行っていた作業など、小さな業務の記載が漏れやすいので注意が必要です。
抜け漏れがないか確認するために、ロジカルシンキング(論理的思考)のフレームワーク「MECE(ミーシー/モレなくダブりなく)」の視点で情報を整理するのも有効です。
さらに、「分からなかったら聞いて」のように口頭での補足説明をあてにせず、すべてドキュメントとして残しておくことが重要です。
前任者が口頭で説明した内容を、後任者がその場ですべて理解できるケースはまず少ないため、どんなに細かいことでも文章として書き残し、あとから後任者が落ち着いて見直せるようにしておきましょう。
慣れている人しか知らないノウハウやTipsも残しておく
引き継ぎ資料には、通常のマニュアルではあまりカバーされない「知る人ぞ知るリアルな情報」も記載しておくとなお良いです。例えば、
- 〇〇部長の承認を得るには、~~のように進めると良い
- 質問するなら△△さんが優しく丁寧に教えてくれるのでおすすめ
- 社員の◆◆さんはチャットを送っても全然返信が来ないので、直接話した方が早い
のように、「泥臭いけれど業務上知っていると有利な情報」を共有しておくと、後任者の思わぬ助けとなるかもしれません。
また、自分なりの効率的な業務の進め方やテクニック、実体験から得た教訓やノウハウ、参考になりそうな書籍やWebサイトといった情報を記載しておくのも効果的です。
資料通りに問題なく業務が進められるか検証する
引き継ぎは、作成したドキュメントを後任者に手渡すだけで終わりにせず、必ず対面またはオンラインでお互いに顔を合わせながら実施するようにしましょう。
資料をもとに後任者に実際の業務を一通り体験してもらい、質疑応答を通じて認識のズレや不明点をその場で解消していきます。
最初は前任者がフォローしながら一緒に業務を進め、徐々に後任者がメインで確実に業務を行える状態まで持っていくことが重要です。
なお、業務を行う中で引き継ぎ資料にまだ書かれていない情報を見つけた場合は、忘れないうちに速やかに資料へと反映させ、常に最新の状態を保つようにしましょう。
5.情シス業務の引き継ぎでよくある課題
ここでは、情シス業務の引き継ぎ時によく見られる4つの課題について解説します。
- 業務が属人化している
- ドキュメントが存在しない/不十分
- 社内に後任者が見つからない
- 引き継ぎを行う時間が足りない
業務が属人化している
1人または少人数で情シス業務に対応している場合、業務の内容や進め方が共有されず、特定の担当者以外には分からない「属人化」の状態に陥りやすくなります。
特に情シス業務は、システムやIT機器、ネットワークなど、ITに関する幅広い専門知識が求められるため、個人のスキルや経験に依存しやすく、とりわけ属人化しやすい傾向にあります。
このような状況では、引き継ぎ用のマニュアルや資料が存在しないことも多く、すべてを1から作成しなければならないため、膨大な時間がかかって非常に大きな負担になります。
場合によっては、言語化すること自体が困難なケースも考えられます。
ドキュメントが存在しない/不十分
情シス業務は、
- やることが多く、日々の業務が忙しい
- 専門性が高く、担当者のスキルや経験に依存しやすい
という特性から、マニュアルや手順書などのドキュメントがそもそも作成されていなかったり、あったとしても情報が古い、または簡単なメモ程度しか残っていないといったケースが少なくありません。
引き継ぎの際に「ドキュメントがない」「情報が整理されていない」状態では、後任者が業務の全体像やノウハウを把握できず、業務を安定して継続できない恐れがあります。
後任者が見つからない
近年の慢性的な人材不足に加え、情シス業務に求められる専門性の高さから、社内外で後任者を確保できない企業が増えています。
情シス業務には高度な専門知識やノウハウが必要となるため、業務を引き継げる人材は必然的に限られ、他部門からの異動による人員確保にも限界があります。
さらに、IT人材の需要拡大に伴い、外部からの採用も非常に困難な状況となっており、中には後任者が決まらないまま担当者が退職してしまうケースも少なくありません。
引き継ぎを行う時間が足りない
情シス業務を少人数で担当している企業の場合、通常業務と並行して引き継ぎ準備を進めなければならず、十分な準備時間を確保できないケースが多く見られます。
特に、「業務量が多い」「無駄な仕事や非効率な作業が多い」といった状況では、日々の業務に忙殺され、引き継ぎのために十分な時間を割けないことがあります。
その結果、後任者に必要な情報を漏れなく伝えることができず、後になって業務の遅延や混乱、トラブル発生の原因となる可能性があります。
6.引き継ぎに関する課題を解決するには?
最後に、情シス業務の引き継ぎ時によくある課題を解決するための効果的な方法を4つご紹介します。
- ナレッジ共有の仕組みづくり
- 自動化による作業の効率化
- 情シス業務の定期的な棚卸し
- アウトソーシングの活用
ナレッジ共有の仕組みづくり
情シス業務の属人化による引き継ぎの失敗を防ぐには、ナレッジを日常的に共有・蓄積する仕組みを作り、必要な時にいつでも参照できる環境を整えることが重要です。
具体的には、次のような取り組みが効果的です。
- 業務マニュアルの作成・更新を日常業務に組み込む
業務手順やノウハウをマニュアル化し、常日頃から更新する運用を定着させます。
マニュアル作成は単発で終わらせず、継続的に更新を行い、常に最新の状態を保つことが重要です。
- 社内ポータルサイトやナレッジ共有ツールを活用する
SharePointやNotion、Microsoft Loopなどの情報共有に役立つツールを活用し、業務に関する情報を1ヵ所に集約します。
これにより、日々の気づきやTipsを複数人で簡単に共有・検索できる環境を整え、ナレッジの蓄積と活用を促します。
ナレッジを「個人の資産」として独占するのではなく、「チームの資産」として共有することを当たり前とする意識づくりが、根本的な解決につながります。
自動化による業務の効率化
引き継ぎ時間が不足している場合は、自動化ツールを活用した業務の効率化が効果的です。
例えば、日次や週次で行う定型作業、通知、社員からの問い合わせ対応などは、RPAツールやAIチャットボットを活用して自動化することで、人間の手で行っていた作業を素早く正確に処理できるようになり、作業負担が大きく軽減されます。
業務の自動化によって、後任者が引き継ぐ業務の量や負担が減り、引き継ぎに必要な時間を短縮できる点は大きなメリットと言えます。
業務の定期的な棚卸し
年に1~2回など、定期的なタイミングで情シス業務の棚卸しを行うことも、スムーズな引き継ぎを実現するうえで非常に有効な方法です。
棚卸しを通じて、「誰が・何の業務を・どのような手順で」行っているのか明らかになり、これまで特定の人しか把握しておらず、属人化していた業務を可視化・共有できます。
さらに、不要な作業や重複している作業の発見にもつながり、棚卸しをきっかけに業務の整理・最適化を進めることで、引き継ぎ内容そのものを軽量化できます。
アウトソーシングの活用
採用難や人材不足といった事情で後任者の確保が難しい場合は、情シス業務のアウトソーシングを検討するのがおすすめです。
もし後任者が決まらないまま情シス担当が退職してしまうと、入退社手続きやヘルプデスク対応、緊急時のトラブル対応などが滞り、業務に大きな支障をきたす恐れがあります。
最悪の場合、会社全体の業務が完全にストップし、事業やサービスの運営が立ち行かなくなるリスクもあります。
アウトソーシングサービスを活用し、自社業務の一部または全部を外部のIT専門企業に委託することで、経験豊富なスタッフによる丁寧なサポートを受けられます。
【アウトソーシングで依頼できる主な業務】
- システム運用・保守
- ドキュメント整備
- サーバー管理
- ネットワーク構築
- 運用監視・障害対応
- 社内ヘルプデスク
- IT機器の設定・キッティング
- セキュリティ対策
- 災害対策
- 業務効率化
など
ポイントは、自社で対応する業務と外部に委託する業務を明確に切り分けることです。
自社では対応しきれない業務や、必ずしも社内の情シスだけで対応する必要のない業務は、外部の専門企業へ積極的にアウトソーシングすることで、作業負担の軽減や業務品質の向上につなげられます。
7.まとめ
いかがでしたでしょうか?
情シス業務の引き継ぎは、企業全体の安定した運営や顧客からの信頼維持に欠かせない重要なプロセスです。
担当者の異動や退職がいつ起きてもおかしくないからこそ、常日頃から業務の見える化やドキュメント類の整備を行い、短時間でスムーズに引き継ぎやすい状態にしておくことが大切です。
なお、社内のリソースだけでは対応が難しい場合や、後任者の確保が難航している場合は、高度なスキルを有する外部人材の力を活用することも有効です。
当社コンピュータマネジメントでは、情シス業務の引き継ぎをはじめ、超上流のシステム企画・要件定義から、下流工程のシステム運用・保守、インフラ構築、セキュリティ対策まで幅広くサポートする「情シス支援サービスION」を提供しております。
デザイン系を除き、IT関連のあらゆる業務に対応可能ですので、ITまわりで何かお困りごとがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
お電話・FAXでのお問い合わせはこちら
03-5828-7501
03-5830-2910
【受付時間】平日 9:00~18:00
フォームでのお問い合わせはこちら
この記事を書いた人
Y.M(マーケティング室)
2020年に株式会社コンピュータマネジメントに新卒入社。
CPサイトのリニューアルに携わりつつ、会社としては初のブログを創設した。
現在は「情シス支援」をテーマに、月3本ペースでブログ更新を継続中。